政党は国民の信を得ているのか(2)
( 前回の投稿の続きとなります。 )
岡田内閣期に発行された『民政』でまず注目したいのは、1936年7月発行の同誌第273号に掲載された「義務教育年限延長開設」というタイトルの山枡儀重(衆議院議員)による論文です。この時期、尋常小学校を卒業する子どもたちの中で多くの子どもたちが次の進学段階で学校教育から離脱し社会に放り出されることを民政党は問題視していました。そこで民政党は、義務教育年限全体を延長することで教育機会の拡充を整えようと提案します。
次号の『民政』(1936年8月発行)では、この義務教育年限改革を特集した内容となっています。この教育制度の整備は重要な政策課題としての関心を集めるようになっていました。『民政』第274号の特集記事である「義務教育年限問題考察の一資料」(立憲民政党『民政』第二百七十四号,民政社,1936年,6-13頁)では、この義務教育年限改革は広田内閣の組閣交渉で問題となった国策樹立運動と連動している政策であると指摘しています。『民政』はその指摘を出発点にして平生釟三郎(文部大臣)による高等小学校改革案について取り上げることとなりました。しかし、義務教育年限改革案は文部省が提案したものでしたが、大蔵省や内閣調査局が改革に伴う財源の課題から同案に反対をしており、政府が一体となって取り組んでいる改革案とはなっていませんでした。だからこそ、民政党自身は、同改革を実行した場合に倍となる子どもたちを収容することになる高等小学校の学課内容をどのように改編すべきであるのかという点に政策研究の関心を寄せています。なぜなら、当然、教師の確保という課題を考慮すれば師範教育のあり方も変えなければならなくなるわけですが、改革に伴って政府がことさら師範教育や学校教育に対して國體明徴や憲政教育という言葉を主張するようになっており、それは間違っていると指摘することが民政党にとっては重要だったからです。國體意識や憲政に関する理解が教師や子どもたちの間で滲透していないのは、国民の権利教育を妨害してきたそれまでの官僚行政の責任であるし、子どもたちの感受力の問題ではないと民政党は指摘しています。このような主張の展開は自由主義的理念をその結党の中心に置く民政党の特徴ですから、民政党を理解しようとするうえで重要なエピソードだといえるでしょう。
内閣が広田に変わると、民政党も政権運営に参加することとなります。広田内閣は2.26事件後に組閣された内閣であり、前回も述べたように軍部がその影響力を発揮したことは確かですが、大変なクーデターとなった事件後の組閣ですから挙国一致が何よりも求められました。民政党や政友会、その他各勢力も政権運営に参加することとなります。政府人事では、各派それぞれに役職が配分されました。そのため、広田内閣の施政とはそれら各政治勢力の思惑が混在して進められるものとなっていきます。ですから、1936年10月発行の『民政』に掲載された記事の多くは、広田内閣の政策を紹介するものとなっています。
このような状況を利用したのが、積極財政に取り組もうとした馬場鍈一(大蔵大臣)でした。第70回議会で巨額な予算を提案した馬場は、その予算案の中に義務教育八年制実施費を計上します。義務教育の年限延長に関してはそれまで大蔵省自らが反対していたはずですが、この時には義務教育の拡張を表明したのです。広田もその施政方針演説で教育改革を国防の充実に次ぐ第二の優先事項として掲げ、義務教育の年限延長を宣言しました。
しかし、この施政方針演説がなされた日、寺内寿一(陸軍大臣)と政友会に所属する衆議院議員の濱田国松との間で激しい論争が起き、予算案の成否どころではなくなってしまいました。当日13時に開会された議会が22時になって天皇陛下に停会を奏請することになったほどの混乱が起きたのです。衆議院議長を経験した濱田が軍部による政党軽視の姿勢を批判したことがきっかけでした。これに寺内が反応し、濱田との間で激しい議論の応酬が起きたのです。結局、この問題が原因となり、広田は内閣を総辞職することとなってしまいます。自然、馬場蔵相によって提案された義務教育八年制実施の予算案も流れることとなり、民政党による教育改革も頓挫することとなりました。
◇◇◇◇◇
広田内閣が寺内と濱田との論争から派生した混乱により総辞職することとなってしまい、予備役陸軍大将であった林銑十郎が後継総理となりました。一度、宇垣一成による組閣が模索されますが陸軍内の反対にあったために、林が内閣を率いることになったのです。しかし、林は広田と異なり民政党とも政友会とも対立を起こします。そのため、解散総選挙において勝利することができず、わずか4カ月で退陣に追い込まれることとなりました。民政党は林内閣が倒閣した直後、1937年6月発行の『民政』で「亡ぶべき者は亡びた」(立憲民政党『民政』第二百八十四号,民政社,1937年,5頁) とさえ表現しています。
林の次に内閣総理大臣となったのが、近衛文麿でした。近衛は、林が政党と対立したことで退陣に追い込まれたことを受けて、「政民両党の二大圧倒勢力と握手」(同上書,6頁)して挙国一致内閣の組閣をまずは目指します。例えば、組閣に及んでは民政党から永井柳太郎を、政友会から中島知久平を閣内に招きました。しかし、政党の影響力が閣議に反映されることを避けるために、近衛がこの両名に対してそれぞれの所属党から離党を求めました。これが、近衛に対する政党の不信感を生むこととなります。組閣直後の『民政』(1937年6月発行)では、「新内閣と政党関係」という論文の中で「近衛新内閣の真意如何」や「前途に一抹の不安感」という見出しを用いており、近衛への抵抗を隠していません。遂には「将来国政を審議するに当つて、政府と政民両党との間に、果たして摩擦なきを得るや否やは予測し難い。吾人は早くも其前途に一抹の不安感なきを得ない」とさえ述べています。
組閣の結果に対しては同論文でも指摘しているように、外務・陸軍・海軍・司法大臣の四職を前内閣から継続して留任させたことは、林内閣と変わりがない内閣であると民政党には映ったようです。民政党は「近衛内閣の推進力が、依然として軍部、就中陸軍である事が、何人の眸底にも歴々として映出するであろう」と危惧を抱いています。しかし一方で、元総理である広田も、広田の内閣で大蔵大臣であった馬場も入閣し、また、近衛の側近である有馬頼寧や安井英二、風見章も内閣に登用されましたので、民政党は「新人を抜擢する人事振り等を見て、近衛首相は必ずしも軍部の推進力に依るロボットならず、自ら一種の成竹を胸中に蔵し、相当の熱意と決心とを以て何事をか策しつゝある」のではないかという期待も寄せるなど、微妙な緊張状態であったと言えるでしょう。
◇◇◇◇◇
そもそも、なぜ近衛が政治改革運動の象徴として担ぎだされることとなったのでしょうか。
民政党は、1937年7月発行の『民政』に「近衛内閣成立行進曲」と題した記事をのせています。同論文の中で、民政党は「軍部、財閥、官僚、政党とこの四つの(中略)対立相克緩和の最も有効な緩和剤として軍部からも政党からもスターとして仰がれたのが『内閣総理大臣公爵近衛文麿』の字面の持つ文化的な革新的な匂ひの高さ」だったと述べています。近衛によって、混迷する政治状況を正常化しようとする意図が、政党側にも軍部側にもそして国民間においても広がっていたことがわかります。続いて、11月発行の『民政』でも、櫻田街人が「国民精神総動員運動批判」と題して、政府による国民精神総動員運動が非常時における政府と政党との対立を緩和し解消することを促すものとして重要であるとの認識を示しています。しかし、近衛と政党のハネムーンは長く続くことはありませんでした。
1938年11月に発行されている『民政』では、民政党は近衛に対して対立姿勢を鮮明にしています。記事「巷説新党運動」の中で、「挙国一致は目標の価値なし」と断言しています。近衛が自ら指導者となって新党をたてる構想が提唱されはじめてから、近衛と民政党の間には政治的な対立が生じ始めました。民政党は近衛の新党運動に対して、そこには何ら政治的イデオロギーがなく、近衛が政府と政党の間に政策の論争を望まないならば帝国議会も憲政もなくすべきだという徹底的な批判を行いました。イデオロギーを以て創られた政党は誰がリーダーになっても存続するが、近衛唯一人の個性によって立党される新党は只の私党であり、近衛の政治的退場があれば即消滅を招くものであると言及しています。そして、そのような政党をなぜ「遮二無二作られねばならぬ」のかと疑問を呈し、最後に「帝国憲法が燦然として不磨の光を放つ、独伊ならぬ我が国に於て、斯かる妄挙は一排すべきである。然らずんば先づイデオロギーを提起し来れ。風吹かば吹け、雨降らば降れ、我党は飽迄乱流の抵柱となり、憲政の軌道を邁進すべきである」と近衛を挑戦しています。
同誌中の他の記事でも、近衛による、ドイツやイタリアの政党独裁を模倣しようとする新党運動は日本の国体や憲法にそぐわないと批判しています。また、近衛の動きは政友会や民政党を壊滅させようとする策略であり、もしくは近衛に近づこうとする政友会がその党勢を再建しようとする政治的工作ではないかと疑っています。最終的に、民政党としては1938年10月20日に開催した幹事会で近衛による新党運動には参加しないことを正式に決定しました。国民精神総動員に関する国民運動に対しては政友会とともに参加することになりますが、近衛が掲げる政策や政治方針と一致した行動をとるということは決して選択しませんでした。例えば、近衛が大陸政策を挙国一致で乗り越えたいと提唱すれば、民政党は日本・満州・大陸による「東亜連盟」の結成を目指して東亜再建運動を展開していきたいと宣言するのです。
近衛に対する批判は、その後の『民政』においても続いています。12月発行の『民政』では、公正な政治は世論による政治でなければならないが、官製世論は専制政治であり、それでは正しい世論を聞くことができないと主張します。翌月号では、馬場恒吾や川口清栄が、近衛が目指してきた新党運動や国民再組織化という政治活動がどのような政治的意図をもって展開されてきたのかについて、それまでの経過を整理しています。近衛内閣が倒れる時も「此更迭は率直に云へば、近衛と平沼との妥協で出来上つた仕事」と酷評しました。近衛内閣の後継である平沼騏一郎内閣はその大臣の半数以上を近衛内閣から継承しましたし、近衛自身も辞職した当日に枢密院議長となって、更に平沼内閣で国務大臣を兼任することとなりましたから、民政党としては当然批判を続けています。その批判は、「何と豪いものだ、これでは近衛は辞職したのか、辞職しないのか分つたものではない。(中略=引用者)内閣更迭と云はんよりは、寧ろ首が代つて一部を動かしたと云ふに過ぎない」と強いものでした。組閣の初めから、近衛に対して民政党は常に警戒心を抱き、近衛が挙国一致の美名のもとに政党を廃そうとするや対立を隠さなくなったことがわかります。1937年から1939年までの期間、近衛の新党運動や国民精神総動員運動に対して、民政党は抵抗を続けていたことがその機関紙で確認することができるのです。
◇◇◇◇◇
西郷隆盛が西南戦争で倒れて以来、政府に抵抗する戦場は帝国議会に移り、国民の民意を代表する政党が発展してきました。ですから、近衛が内閣をはじめて率いた時、挙国一致を旗印に既存政党を吸収するか解体するかを目論まなければその政権基盤が安定することはなかったことは政略としては理解できます。しかし、民政党の抵抗によりその最初の思惑は失敗しました。しかし、近衛が再び政権首座に就くや、近衛の政略に抵抗するべき政党の指導者側からみずから「政党」の消滅を自ら招こうとする発言が発せられるのです。
政友会総裁の久原房之助が、米内光政内閣が1940年1月の組閣当初より陸軍と対立していたことからその内閣の存続は長くは続かないと考えたのか、近衛の新体制運動に関連して「若し国家の為必要とあらば、相率ゐて党を解き、新たに一大強力政権を樹立する事も、亦敢て辞すべきではないのである」(立憲民政党『民政』第三百十九号,民政社,1940年,8頁)と政友会党大会で演説したのです。民政党は、この久原の発言に反応し、近衛による新党運動が再び民政党を襲うのではないかと警戒の眼を向けました。
民政党は7月発行の『民政』の巻頭で、政友会の久原が唱える政党解党論に対して、「挙国一致は時の声である。(中略)併し乍ら、(中略)それ〲の存在理由を持って立党したものが、単に非常時なるが故にといふが如き、曖昧な一片の理由を以て無造作に解党出来るものではない」と論じます。政策や立党理念があって政党は存在しうるものであり、それを無視した合従連衡を民政党は否定しました。久原は民政党の総裁である町田忠治に対して両党の解党を直接説きますが、町田はこの提案を拒否しています。この間の動きは、次号の『民政』(1940年8月)に掲載の「立憲民政党解党始末」に詳しく報告されています。
しかし、久原の動きに対して、やがて政友会革新同盟の中島知久平も近衛が新党の党首になるという条件ならばとその合流に同意します。この動きによって、近衛新党に対して反対の姿勢をとるのは民政党のみとなりました。久原たちの行動は新党を作る上での主義主張やイデオロギーの確定も必要とせず近衛唯一人の個性に依存するという構想でしたから、民政党は日本の政治体制はドイツのナチスやイタリアのファシズムでもないと彼らの行動を批判しました。衆議院議員の北昤吉や村松久義も『民政』に、近衛の新党運動に対する批判を寄稿しています。北昤吉の『近衛公昭和維新の据膳に座す』と村松久義の『新しき原理への欲求』は、ともに「新政治体制の批判と考察」というテーマでまとめられた論文です。また、池田生も『新党運動鳥観図』の中で、新党運動を主導するグループを①末次信正元内務大臣による「既成政党打破、新興勢力糾合」を目的とする一派、②中島による民政党への攻撃を主に挙げて「民政の大合同」を目的とする一派、③風見章による「産業組合を母体として新政党を樹立」することを目的とする一派の3つのグループに分け、其々の政治的意図を整理したうえで民政党は伝統ある政党としての矜持を失ってはならないと主張しました。
◇◇◇◇◇
近衛を担ぐ新党運動が攻勢を強める中で、民政党はその動きに抵抗するために新たな政綱を宣言します。東亜新建設という戦争目的を果たしたいという政治課題を近衛が掲げるならば、民政党もその目的に同意しながら政党としての独自の見解を示すことで、解党の圧力を撥ね付けようとしたのです。戦時体制の構築を達成するための「効率性」を近衛は政治的に利用しますから、その新体制の整備方法如何に民政党の命脈を残そうとするものであったと推測します。
民政党が独立した政党として近衛に抵抗しようとする姿勢は政綱の宣言だけでなく、近衛の組閣の前に党大会に代わる会議として開催した両院議員評議員連合会の内容にもみてとることができます。席上で、総裁である町田忠治は「我国興隆の本、全く茲に存する、彼の共産、独裁の如き元より断じて之れを容れない」(立憲民政党『民政』第三百二十二号,民政社,1940年,5頁)と発言しました。この町田の発言は、近衛に対する批判であったといえるでしょう。しかし一方で、町田は近衛政権が既存政党を併呑しようとしていることに対して国民の支持が高まりつつあったことも理解していたのではないかと考えます。町田はその演説の中で、民政党が新たに掲げた政綱と宣言を念頭に「以上は他の党派と対立的意識を有するものではない、苟しくも此政綱と所見を一にし、憲政に関し信念を同じくするものあるに於ては進みて之と一体となり、共に国政に尽す事は決して躊躇するものではない(中略)近衛公が時代に適応する新政治体制の確立を提唱せられた、其の趣旨には賛同する」(同上書,6-7頁)と述べたことは、事実上、近衛政権に降伏する時がいずれ到来することを予期するかのような発言でもあったと思えます。ですが、先にもあげた1940年8月発行の『民政』では、新党運動によって他の既存政党がいとも簡単に解党に向かう様を批判する論文「三百万党員の奮起をも熱望す」を掲載していますから、民政党の矜持として最後まで近衛に抵抗する姿勢を崩そうとしていなかったことは確かでしょう。
しかし、それほど抵抗していた民政党も、党内から多くの離党者や近衛新党への合流を主張する者が続出しはじめたことで遂に改進党以来60年に及ぶ歴史に終わりを告げるときがやってきます。解党大会の報告では「立憲民政党六十年の最後の幕を閉づる解党大会」(同上書,94頁)とそれを表現しました。民政党解党のきっかけを作ったのは、近衛の第一次政権期から民政党を代表して内閣の大臣の座にあった永井柳太郎でした。「自分は最後の一人たるとも踏止まつて民政党を守る」(同上書,21頁)と公言していた永井自身が、35名の同志を連れて民政党を離党し、近衛の下に参じたのです。
永井は、斎藤実・近衛文麿・阿部信行の三内閣で大臣を務めた民政党の「一枚看板」 の政治家として、将来の総理候補として目されていた国民的人物でした。早稲田大学雄弁会での活躍で大隈重信に認められてオックスフォード大学に留学した後、帰国して母校である早稲田大学で教員となった永井は、大隈の政治的遺伝子を直接受け継ぐ人物の一人だったといえるでしょう。ですが、既に阿部内閣の頃から永井と近衛の親密さは世上に知られていました。永井は「将来一党を率うる事のあるべき彼には政権請取人としての可能性が濃くなる事も想像され得る」(角屋謹一『戦時下の政界人物展望 : 昭和政治家評論』私家版,1939年,6頁)と評価されるほどの政治的実力を有していましたから、それはすなわち一方で民政党の消滅を永井が招来することができる実力があることをも意味していたとさえ言えるのではないでしょうか。永井自身は、「藩閥の横暴に対し、党を挙げて大義に殉ずるの意気を以て改進、自由両党を解き単一戦線を結成したる大隈、板垣両大先輩の英霊に見ゆるを得ん」(前掲 『民政』第三百二十二号,106頁) という決意で、脱党宣言を行いました。近衛を通して経済格差にあえぐ国民を救うために新党運動・新体制運動を自分が選択したことを、大隈が成し遂げた維新の実現と民意の反映という大業に写し見ようとしたのです。
いずれにせよ、この離党騒動が直接のきっかけとなり、民政党は1940年8月15日の党大会で解党を宣言します。永井は近衛の側近として、近衛の新党が立ち上がる前に既成政党が解散しなければその所属議員は近衛新党を準備する委員会のメンバーには入れないとの考えを披露し、民政党の解散が一日でも早くなるように追い込みました(同じような選択を迫ることでその約束されたであろう将来の成功を失敗させてしまった政党や政治家が現在に至るまで多く再生産されたのは、皮肉なことだなと思います。やはり、歴史は証明していると思います)。尚、民政党は解党にあたり、大隈重信の墓参りを行うことを決議しています。これは、大隈の後継であるとの自負が永井だけでなく民政党にもあったことを示したものでした。
政党としての存在の民政党は消滅しますが、その機関紙である『民政』は存続します。「立憲民政党機関」の名称を「国策指導機関」に変えて、民政社が発行所のまま存続することとなるのです。また、民政党の政務調査館の管理を継続する団体として、財団法人櫻田会が結成されました。1940年9月発行の『民政』での「雑誌『民政』甦生の辞」では、「新体制運動が時代の勢を制し、澎湃として漲り来る大波の如く、ヒタ〱と凡ての岸を洗つて、伝統を一掃せんとするといつても、独り明治天皇の欽定憲法は、巨巌の如く現存する。(中略)我等は近衛公と共に、其新体制運動を監視して、絶対に憲政を乱るが如きなからしめむことを欲する」と宣言しています。これは、はっきりと近衛に対して政治的挑戦を表明した文章だと言えるでしょう。さらに、近衛による声明「新政治体制の理念と構想」を同誌で掲載しながら、近衛の独裁を支える政治理論「衆議統裁」は帝国憲法下にある帝国議会の権力を侵すことができない、と表明しました。衆議統裁とは「衆議を最後に総裁一人の意思を以て決定するという決議方法」という意味です。そして、筑波四郎が「集議制と翼賛体制」と題する論文を通して、帝国憲法五条に示す議会の協賛という言葉の意味を伊藤博文による憲法案起草の過程を追いかけながら整理し、近衛が国家の立法権を独占しようとしたのを批判しました。
しかし、民政党の消滅により、政府や政治指導者が掲げる政策に対して対案を提示し議論する公的な政治組織の存在はその後出てきません。政府内外共に政策や政治構想が活発に議論されるのは、敗戦後を待たねばならなくなるのです。1945年8月15日が日本再生に向けて新たな出発となった敗戦日ならば、1940年8月15日は日本の近代政党政治が終幕した日であったと私は考えます。
しかし、政党が崩壊した理由は、政党側にも大きな責任があったはずです。国民が既存政党を信用していなかったという一面はやはり何より重要な現実だったと考えます。これまで長く政界に籍をおいた政治家たちを「信用」をするに足るリーダーとして国民が認めることができないのならば、政権交代でとどまるのではなく新たな新陳代謝・人材交替が必要でしょう。しかし、その交替にあっては独裁的なリーダーたらんとする野心は日本では成功しないことも私達の歴史が証明しています。
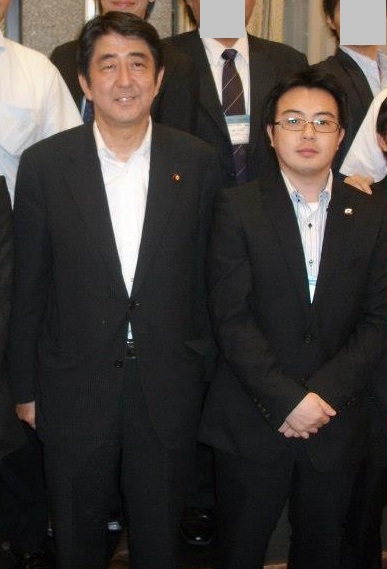
さて、独裁的な野心を持つ者は必ず失敗する私達の国の、令和というこの時代の政治改革では、どのような日本創生を目指すのか、明確な針路を示すことができるのは、いったい誰なのでしょうか。私は安倍総理が偉大であったのは、「戦後レジームの脱却」という旗を掲げて次に目指すべき社会像を国民に選択肢として明確に提示できたことだと思います。安倍政権への評価をどのように行うかは人それぞれでしょうが、少なくとも国家のリーダーたらんとする方々は国民の多くが信用に足ると安心できることができるリーダーシップや構想力を示してほしいと私は思います。安倍総理は国民の合意をどこまでも得る努力を続けて、悲願を達成されようとしました。そのようなエネルギーを他のリーダーたちにも感じたいと思います。そのリーダーが目指す社会像を国民の前に選択肢として提示してほしいと思います。私は、国家のリーダーたちに「何のために政治家をやっているのですか?」と否定的に問いかけたりはしたくありません。


